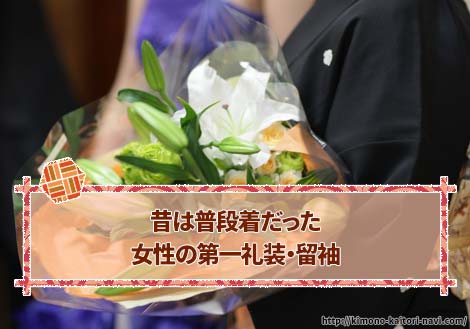
女性の第一礼装・留袖。
身内の結婚式に参列するなど、もっとも格調の高い場で着用します。
留袖には、黒留袖と色留袖の2種類があります。
黒留袖は既婚女性のみが着用できますが、色留袖は未婚者でも着られます。
昔は普段着だった留袖
「留袖」の元々の意味は、未婚女性が結婚し、振袖を短くしたところに由来します。
振袖は、未婚女性にとって愛情表現の手段でした。
ところが結婚するとその必要がなくなるので、袖を短くしたわけです。
このとき袖を「切る」という言葉を使うと、「縁を切る」ということにつながります。
そこで切るではなく「留める」と呼んだことから、「留袖」の言葉が生まれました。
江戸時代までは留袖は、単に「袖を短くした着物」というだけで、未婚女性が普段に着るものでした。
それが変わったのは、明治時代になってから。
明治時代に西洋から「ブラックフォーマル」の概念が取り入れられました。
それにより、黒染めに五つ紋を入れ、裾にのみ柄を配した着物が既婚女性の第一礼装とされ、これが「留袖」と呼ばれるようになりました。
留袖は明治時代に、普段着から最も格の高い着物へ変化したというわけです。
留袖の種類は2種類
黒留袖
黒留袖は結婚式や披露宴のときのみ、しかも新郎新婦の近親者や仲人の奥さんだけが着用します。
地模様のない縮緬を黒く染め、裾に飲み模様を配し、五つ紋が入ります。
色留袖
色留袖は黒以外のものを指しますが、黒留袖ほど形が決まっているわけではなく、着用の場によって紋の数や着方を変えます。
また色留袖は、既婚女性だけでなく未婚女性も着用できます。
色留袖も格式が高いので、黒留袖ほどではないにせよ、着用の場は限られます。
ただし最近ではあまり堅苦しく考えず、家族・近親者のお祝いの気持ちを表すときなら、どのような場でも着用できるようになりつつあります。








